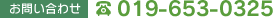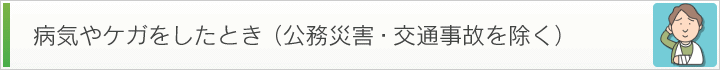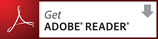- トップページ
- 短期給付(医療保険)
- 給付の種類・内容
- 病気やケガをしたとき
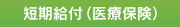

*このページ内の見出し項目です。クリックすると、該当箇所にジャンプします。
- 6 移送費・家族移送費
- 7 高額療養費
- 8 高額介護合算療養費
- 9 一部負担金払戻金・家族療養費附加金
注 「医療給付のしくみ」を併せてご覧ください。
マイナ保険証について
組合員証等の新規発行(再交付を含む)は令和6年12月1日で終了し、令和6年12月2日からの医療機関の受診は、マイナ保険証の御利用が基本となります。お手元の組合員証等が経過措置で利用できるのは「令和7年12月1日まで」です。
(Q&Aはこちらをご覧ください。)
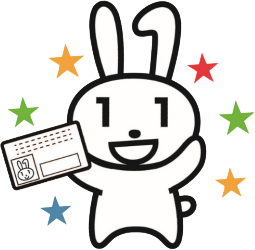
マイナ保険証を持っている方 ~資格情報通知書が交付~
医療機関等の受診はマイナ保険証の利用が基本となります。
新加入の組合員及び被扶養者(任意継続による加入を含む)の方には、個人番号登録後に「資格情報通知書」(注)を交付します。
- 注1
- 組合員等記号番号は「資格情報通知書」に記載されています。この通知書の情報はマイナポータルの健康保険情報でも知ることができます。
- 注2
- マイナ保険証の利用を解除したいときは、こちらをご覧ください。
マイナ保険証を持っていない方 ~資格確認書及び資格情報通知書が交付~
医療機関等の受診は、「資格確認書(カード型)」を利用してください。
これまでの組合員証等と同じく使用することができます。有効期間は発行から5年間です。
個人番号登録後に発行されますので、お手元に届くまで数週間かかることがあります。
なお、医療機関受診の際は、高齢受給者証や限度額適用・減額認定証認定証等が従前のとおり必要です。
マイナ保険証の受付が上手くいかなかった場合はこちら(厚生労働省リーフレットP2)
1 療養の給付・家族療養の給付
マイナ保険証等を使用して保険医療機関で受診した場合に、次の額を医療機関に支払います。
| 区分 | 共済組合の給付 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 小学校就学前の者 | 医療費の8割 | 医療費の2割 |
| 小学校就学以後から70歳未満の者 | 〃 7割 | 〃 3割 |
| 70歳以上75歳未満の現役並み所得者 | 〃 7割 | 〃 3割 |
| 70歳以上75歳未満で現役並み所得者でない者 (昭和19年4月1日以前に生まれた者) |
〃 9割 | 〃 1割 |
| 70歳以上75歳未満で現役並み所得者でない者 (昭和19年4月2日以降に生まれた者) |
〃 8割 | 〃 2割 |
注 「現役並み所得者」とは、標準報酬月額280,000円以上の組合員とその被扶養者をいいます。
2 療養費・家族療養費
やむをえない事由(旅行先でマイナ保険証等を持っていなかった場合など)によりマイナ保険証等を使用せず医療機関で受診したとき、治療上必要なコルセット等を購入したときなどは、請求により上記の額を組合員に支給します。
5 訪問看護療養費・家族訪問看護療養費
組合員又は被扶養者が、病気等により在宅で療養し、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けた場合に、訪問看護に要した費用の7割(3割は自己負担)を指定訪問看護事業者に支払います。
7 高額療養費
窓口支払額が次の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を組合員に支給します。
| 標準報酬月額 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 830,000円〜 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(140,100円) |
| 530,000円〜790,000円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(93,000円) |
| 280,000円〜500,000円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(44,400円) |
| 〜260,000円 | 57,600円(44,400円) |
| 市町村民税非課税者 | 35,400円(24,600円) |
| 区分 | 標準報酬月額 | 外来(個人ごと)・入院がある場合(世帯単位) | |
|---|---|---|---|
| 現 役 並 み 所 得 者 |
現役並みⅢ | 830,000円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1/100 (4回目から140,100円) |
| 現役並みⅡ | 530,000円〜790,000円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1/100 (4回目から93,000円) |
|
| 現役並みⅠ | 280,000円〜500,000円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1/100 (4回目から44,400円) |
|
| 区分 | 外来(個人ごと) | 入院がある場合(世帯単位) | |
| 一般 | 18,000円 (年間上限 144,000円) |
57,600円 (4回目から44,400円) |
|
| 低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得者Ⅰ | 15,000円 | ||
注1 表2中「現役並み所得者」とは標準報酬月額280,000円以上の組合員とその被扶養者をいい、「低所得者Ⅱ」とは市町村民税非課税者をいい、「低所得者Ⅰ」とは市町村民税に係る所得がない者をいいます。
注2 ( )は直近の1年間に4回以上該当したときの限度額です。
限度額適用・減額認定証について
保険医療機関での医療費が高額となる場合は、マイナ保険証を利用すると、自己負担限度額のうち高額療養費相当額の支払いが免除され、後日、共済組合がこの額を医療機関に支払います。
マイナ保険証をお持ちでない方は、医療機関等から認定証の提示を求められたときは申請が必要です。
なお、市町村税非課税者に該当する方が限度額・標準負担額の減額認定を受ける場合は、共済組合又は所属所の共済組合事務担当課(総務課等)に申請が必要です(申請書「各種様式ダウンロード-短期関係-34_限度額適用等認定申請書」)。
特定疾病療養受療証について
腎透析(人工腎臓)・血友病・後天性免疫不全症候群患者の方は、共済組合が交付する「特定疾病療養受療証」を保険医療機関に提示すると、自己負担額が1件10,000円(標準報酬月額530,000円以上の腎透析患者は20,000円)となり、それを超えた額については、共済組合が当該医療機関に支払います。
8 高額介護合算療養費
1年間(8月1日から翌年7月31日)で世帯が負担した医療費と介護費が、次表の一定の基準を超えた場合、申請によりその超えた額を組合員に支給します。
| 標準報酬月額 | 医療保険と介護保険の自己負担額 | |
|---|---|---|
| 平成26年8月〜27年7月 | 平成27年8月〜 | |
| 830,000円〜 | 1,760,000円 | 2,120,000円 |
| 530,000円〜790,000円 | 1,350,000円 | 1,410,000円 |
| 280,000円〜500,000円 | 670,000円 | 670,000円 |
| 〜260,000円 | 630,000円 | 600,000円 |
| 市町村民税非課税者 | 340,000円 | 340,000円 |
| 区分 | 医療保険と介護保険の自己負担額 | |
|---|---|---|
| 現役並み 所得者 |
標報月額830,000円以上 | 2,120,000円 |
| 標報月額530,000円〜790,000円 | 1,410,000円 | |
| 標報月額280,000円〜500,000円 | 670,000円 | |
| 一般 | 560,000円 | |
| 低所得者Ⅱ | 310,000円 | |
| 低所得者Ⅰ | 190,000円 | |
注1 現役並み所得者、低所得者Ⅰ.Ⅱの定義は、高額療養費欄中の注1を参照のこと。
注2 医療保険分は、自己負担額から共済組合から支給される高額療養費・附加給付を控除した額が計算対象となります。